初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00

相続において、遺言書で相続財産の全てが一部の相続人に渡ると指定されていた場合、他の相続人がまったく財産を受け取れないという事態が起こることがあります。これを防ぐために、日本の相続制度には「遺留分」という権利が認められています。遺留分侵害額請求権は、法定相続人に最低限保証されている権利であり、これにより相続人は一定の相続財産を請求することができます。本記事では、遺留分侵害額請求権の基礎知識とその手続きについて、初心者向けにわかりやすく解説します。
【関連動画】遺留分侵害額請求とは?基礎知識と実際の手続き【相続のための弁護士チャンネル】
遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分のことを指します。被相続人が遺言書で財産の配分を指定したとしても、遺留分を侵害する内容であれば、相続人はその分を請求することができます。遺留分の制度は、相続人が相続財産を全く受け取れなくなることを防ぐために設けられています。
遺留分は法定相続人に認められる権利ですが、配偶者と子供、直系尊属に限られています。全ての相続人に適用されるわけではなく、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。
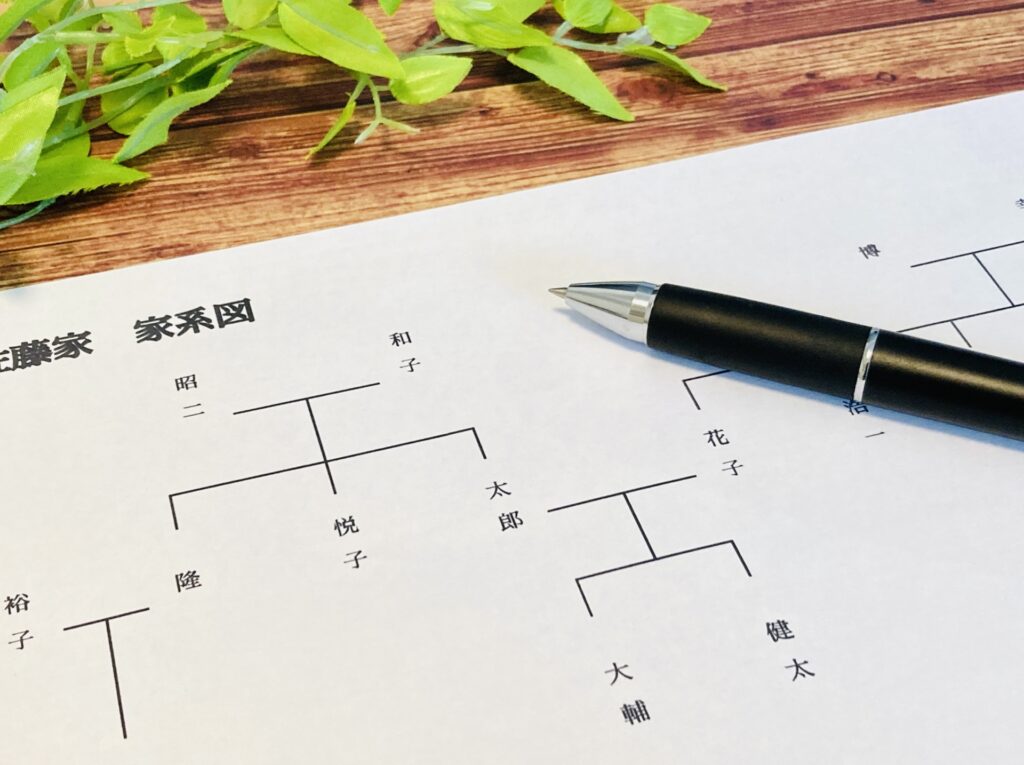
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち一部の人です。具体的には、以下の人が対象となります。
一方、兄弟姉妹には遺留分請求権が認められていません。これは、兄弟姉妹が相続の対象になるのは、配偶者や直系親族がいない場合に限られるためです。

遺留分の割合は、法定相続分に基づいて定められています。被相続人が誰を相続人に残すかによって、遺留分の割合は以下のように変わります。
たとえば、被相続人が配偶者と2人の子供を残して亡くなった場合、遺留分は配偶者が1/4、子供2人で1/4(1人あたり1/8)となります。

遺留分が侵害されている場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、相続財産の一部を請求できます。以下のステップで請求手続きを進めます。
遺留分侵害額請求権には期間の制限があります。請求できる期間は以下の2つです。
この期間内に請求を行わないと、遺留分請求権は失効してしまいます。
遺留分侵害額請求の手続きは、基本的に以下のような流れで進められます。
話し合いがまとまらない場合や相手方が支払いを拒否した場合、次の段階として調停や訴訟を検討することになります。
遺留分侵害額請求にはいくつかの注意点があります。
【関連動画】相続で揉めないために今できること 【相続のための弁護士チャンネル】
遺留分は、法定相続人に最低限の財産を確保するための大切な権利です。しかし、遺留分侵害額請求を行う際には、感情的なトラブルや法的な手続きが絡むため、正確かつ冷静に対応することが求められます。遺留分請求を行う場合は、請求期間を守り、早めに対応を進めることが重要です。また、専門家のサポートを得ることで、スムーズに解決を図ることができます。
【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有
交通アクセス:
電話受付時間:
平日 9:30~18:00
電話番号:
06-6131-0288
対応エリア:
全国各地
相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。