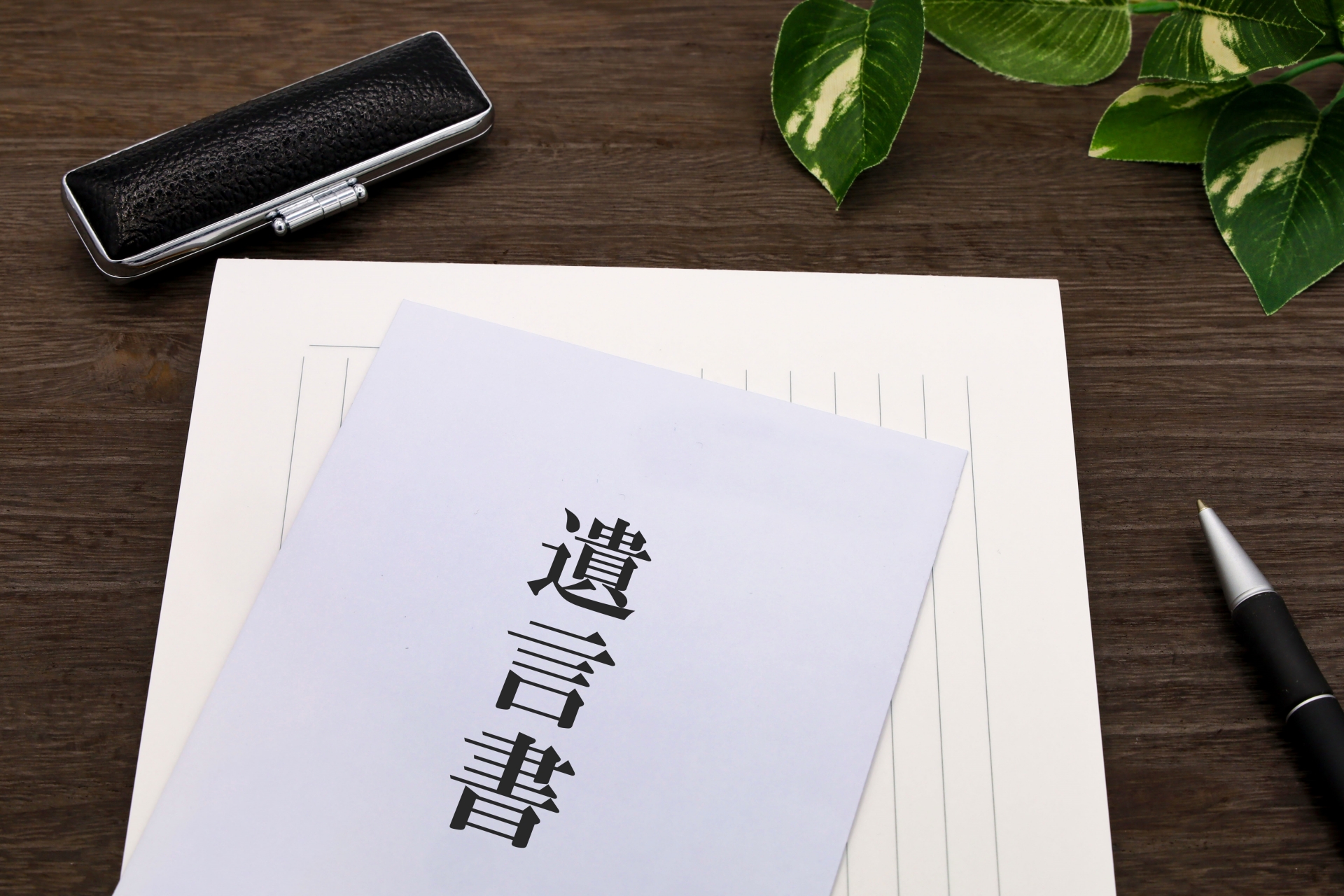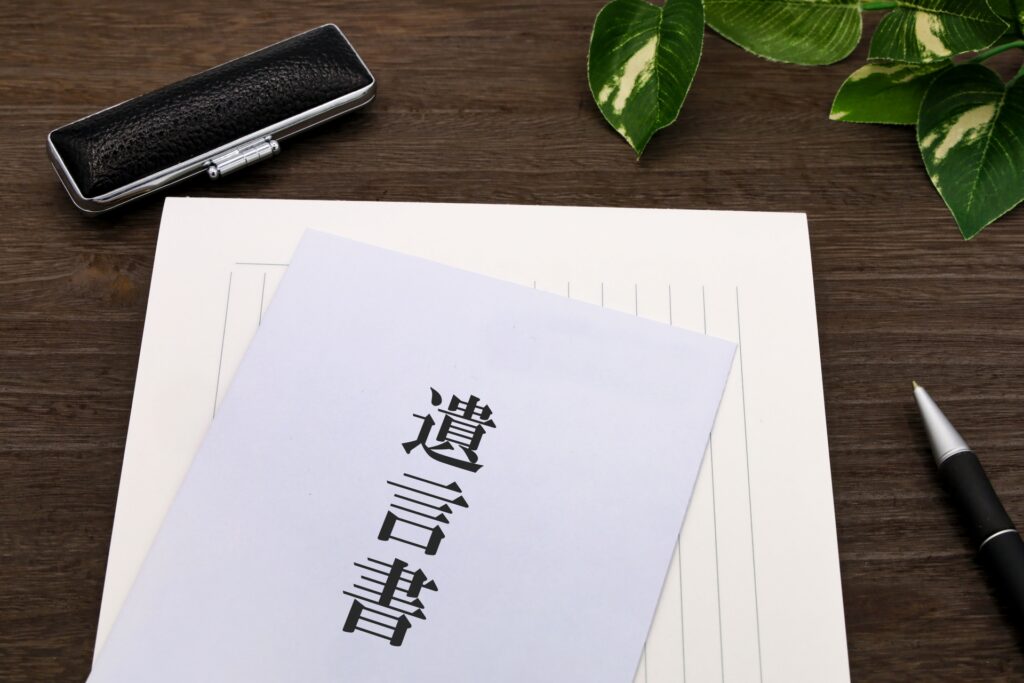遺言書は、遺産をどのように分けるかを明確に伝えるための重要な文書です。家族の間でのトラブルを防ぎ、遺志を確実に実現するためには、正しい知識と準備が必要です。本記事では、遺言書を作成する際に押さえておきたい5つの重要なポイントを解説します。
【関連動画】遺言はいつ作成する?ベストな時期を弁護士が解説【相続のための弁護士チャンネル】
目次
1. 遺言書の種類を理解する

遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれに特徴があるため、自分の状況に合わせて選びましょう。
1.1 自筆証書遺言
- 特徴:遺言者が全文を手書きで作成する形式。(ただし、目録等はワープロ印字でも良くなっています。)
- メリット:簡単に作成でき、費用がかからない。
- デメリット:形式不備や紛失のリスクがある。
1.2 公正証書遺言
- 特徴:公証人が作成する遺言書。
- メリット:法的要件を満たし、紛失や無効のリスクが低い。
- デメリット:公証役場への手数料が発生する。
1.3 秘密証書遺言
- 特徴:内容を秘密にしたまま公証人に保管を依頼する形式。
- メリット:内容を他人に知られず保管できる。
- デメリット:形式の不備があると無効になる可能性がある。
2. 遺言書に記載すべき内容
遺言書には、以下のような重要な内容を記載します。
2.1 遺産の分割方法
- 具体的に、誰にどの財産を渡すのか明確に記載します。例:○○市○○町の土地を長男に相続させる。
2.2 遺言執行者の指定
- 遺言の内容を実行するための「遺言執行者」を指名することで、スムーズな手続きが可能になります。
2.3 特別な配慮
- 介護をしてくれた人への特別な遺贈や、寄付を希望する場合など、遺産分配に関する特別な意思も記載することができます。
【関連動画】遺言の作り方、せっかく作ったのに無効になってしまう遺言書とは?【相続のための弁護士チャンネル】
3. 法的要件を満たす遺言書の書き方
遺言書は法的に有効でなければ、後々無効とされる可能性があります。以下のポイントに注意してください。
3.1 日付を正確に記載する
- 遺言書には日付を正確に記載します。「○○年○○月○○日」と具体的に記載する必要があります。
3.2 遺言者自身が署名・押印する
- 自筆証書遺言の場合、遺言者自身が全文を手書きし、署名・押印が必須です。
3.3 明確な意思表示
- 曖昧な表現は避け、具体的かつ明確に遺産分割を指示します。
4. 遺留分と配慮のポイント

遺言書で自由に遺産分配を決めることができますが、「遺留分」という制度を考慮する必要があります。
4.1 遺留分とは?
- 法律で定められた、特定の相続人が最低限受け取る権利のことです。配偶者や子ども、親が対象になります。
4.2 配慮のポイント
- 遺留分を侵害すると、相続人間で争いになる可能性があります。事前に弁護士などに相談し、適切な配分を検討しましょう。
5. 専門家に相談する重要性
遺言書の作成には、法的な知識と注意が必要です。以下の理由から、専門家に相談することをおすすめします。
5.1 法的トラブルの防止
- 弁護士や司法書士に相談することで、法的に無効となるリスクを防げます。
5.2 家族間の争いを防ぐ
- 適切なアドバイスを受けることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
5.3 確実な遺志の実現
- 遺言執行者の選定や遺言内容の具体化を専門家と一緒に進めることで、遺志を確実に実現できます。
まとめ
遺言書を作成することは、家族への思いやりを形にする大切な手続きです。この記事で紹介した5つのポイントを参考に、正確でトラブルのない遺言書を作成しましょう。
【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】
遺言書に関するご相談はこちらまで
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有
交通アクセス:
- 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A番出口)徒歩5分
- JR環状線「天満駅」徒歩6分
- 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分
- 泉の広場(M10階段右上がる)徒歩6分
電話受付時間:
平日 9:30~18:00
電話番号:
06-6131-0288
対応エリア:
全国各地
相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。