初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00

遺産分割協議は、相続人全員が合意に至ることで初めて成立します。しかし、協議が難航し、相続人間で意見がまとまらない場合には、次のステップとして適切な対処法を取る必要があります。この記事では、遺産分割協議が成立しない場合の具体的な対処法について、ステップごとに詳しく解説し、トラブルを解消するための方法を紹介します。
【関連動画】遺産分割協議のやり方 協議が成立しない場合どうなるか【相続のための弁護士チャンネル】
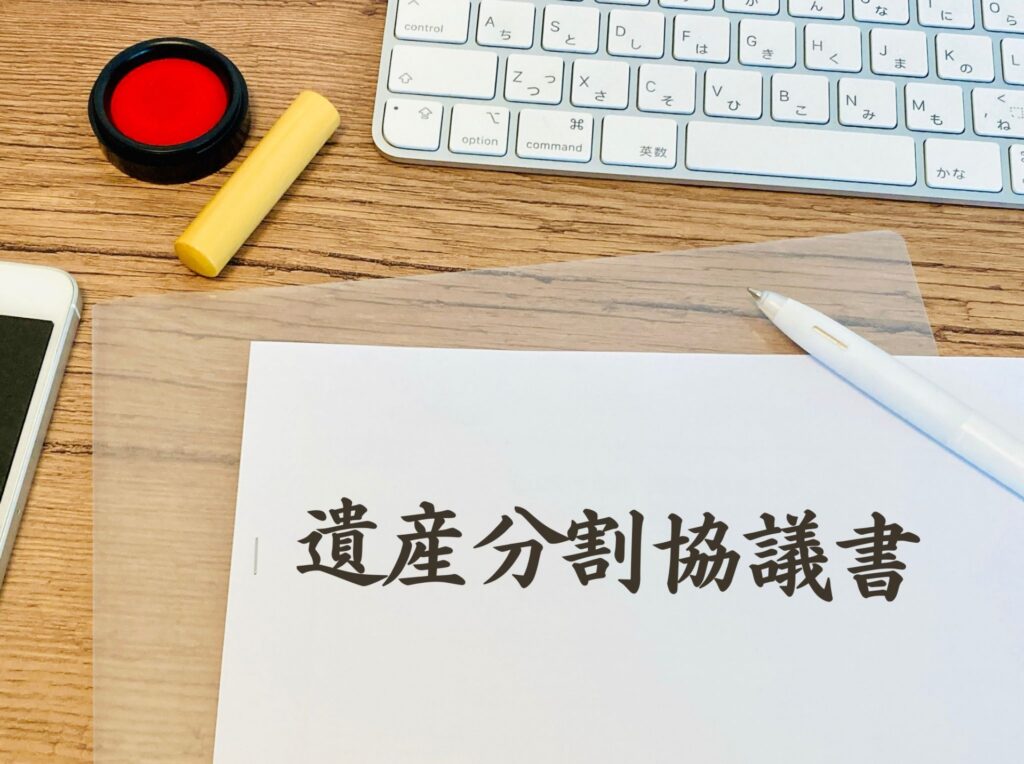
遺産分割協議は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分割するか話し合い、合意に基づいて遺産を分配するための協議です。協議が成立するためには、法定相続人全員の同意が必要です。遺言書がない場合は、取得する遺産の価値は法定相続分に基づいて分割されるのが通常ですが、遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる分割方法も可能となります。
被相続人に遺言書がある場合は、遺言書の内容に基づいて相続手続が行われますので、すべての相続財産について遺言で指定されている場合は遺産分割協議を必要としません。
遺産分割協議が成立しない原因にはさまざまな理由があり、それぞれに応じた解決策が必要です。
相続人が複数いる場合、それぞれの利害や意見が対立することがあります。特に、遺産の種類や価値に関して意見が食い違うと、合意に至るのが難しくなります。感情的な問題や過去の家族間のトラブルが原因で、協議が進まないこともあります。
財産の評価が不明確だったり、不動産や株式などの分割が難しい財産が含まれる場合、相続人間で評価や分割方法について不満が出やすいです。特に、現物分割が難しい財産(不動産など)が含まれている場合、どのように分配するかで対立することがあります。
家族間の過去の問題や、被相続人が亡くなるまでの介護や金銭的支援を巡る感情的な対立が原因で、遺産分割協議がまとまらないことも少なくありません。この場合、感情が先立ち、冷静な話し合いができないことがあります。
【関連動画】遺産分割はよく揉める?なぜ争いになるのか【相続のための弁護士チャンネル】

協議が成立しない場合でも、冷静に対処し、次のステップに進むことで解決策が見えてきます。
まずは、相続人同士で再度話し合い、合意に至るよう努力することも考えられます。相続人のみでの話合いが困難である場合は、弁護士などの第三者が入ることも考えられます。第三者の仲介を依頼することで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いができる場合もあります。家族間での合意が難しい場合、早めに専門家に相談することも検討しましょう。
相続人間で話し合いがまとまらず、対立が深刻な場合、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。調停では、裁判所が任命する調停委員が相続人の意見を聞き取り、公平な解決策を提案します。調停は、話し合いによる解決を目指すため、裁判よりも柔軟な対応が可能です。
調停で合意に至らない場合、最終的には家庭裁判所の審判に移行します。審判では、裁判官が相続財産を法的にどのように分割するか決定します。審判での決定には法的な強制力があり、相続人全員がその決定に従う必要があります。

調停を申し立てる際には、家庭裁判所に調停申立書を提出し、手続きを開始します。申立書には、相続人全員の氏名や相続財産の一覧、分割に関する主張を記載します。申立手数料や収入印紙、郵便切手も必要です。
調停の期日には、相続人全員が家庭裁判所に出席します。調停委員が各相続人から意見を聞き、公正な話し合いを進めます。場合によっては、相続人同士が顔を合わせずに調停を進めることも可能です。
調停が不成立の場合、家庭裁判所は審判に進み、裁判官が最終的な分割方法を決定します。審判では、法的なルールに基づいて財産が分割され、相続人の意見が反映されにくい場合もあります。
審判では、裁判官が相続財産の評価や分割方法を決定し、強制的に分割が行われます。審判の結果に異議が出ない場合は、法的拘束力があり、相続人全員がその決定に従う義務があります。

遺産分割協議が成立しない場合、専門的な知識が必要になることが多いため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は法律的なアドバイスを提供し、公正で迅速な解決を図るためのサポートをしてくれます。また、調停や審判に移行する際にも、専門家の支援があればスムーズに進めることが可能です。
【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有
交通アクセス:
電話受付時間:
平日 9:30~18:00
電話番号:
06-6131-0288
対応エリア:
全国各地
相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。