初回相談無料
06-6131-0288
【受付時間】平日9:30〜18:00

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け取らないという意思を示し、法的に相続人としての地位を放棄する手続きです。相続放棄を行うと、相続人としての権利や義務が一切なくなり、借金などの負債も引き継がないという大きな利点がありますが、一定の条件を満たさなければなりません。本記事では、相続放棄が認められるための条件と具体的な例を解説します。
【関連動画】相続放棄と限定承認の違いを解説【相続のための弁護士チャンネル】
相続放棄は、以下の条件を満たしている場合に家庭裁判所に申請し、認められる手続きです。
相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった日)を知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。この3か月の期間は、相続人が被相続人の財産や負債の状況を把握し、相続するかどうかを判断するための「熟慮期間」と呼ばれます。期限を過ぎると、相続放棄はできなくなり、財産も負債も引き継ぐ「単純承認」と見なされます。
相続放棄は、相続の開始を知った時点からカウントが始まります。つまり、被相続人が亡くなったことを知っていない場合、相続開始とは見なされず、放棄の期限は発生しません。ただし、いったん相続を知った後は、すぐに財産や負債の確認を進め、適切な判断を行う必要があります。
相続放棄は、相続人本人が自らの意思で行う必要があります。親族や他人が代わりに放棄することはできません。ただし、未成年者や成年後見人がいる場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)が代理で手続きを行うことが認められます。
【関連動画】相続放棄の注意点【相続のための弁護士チャンネル】
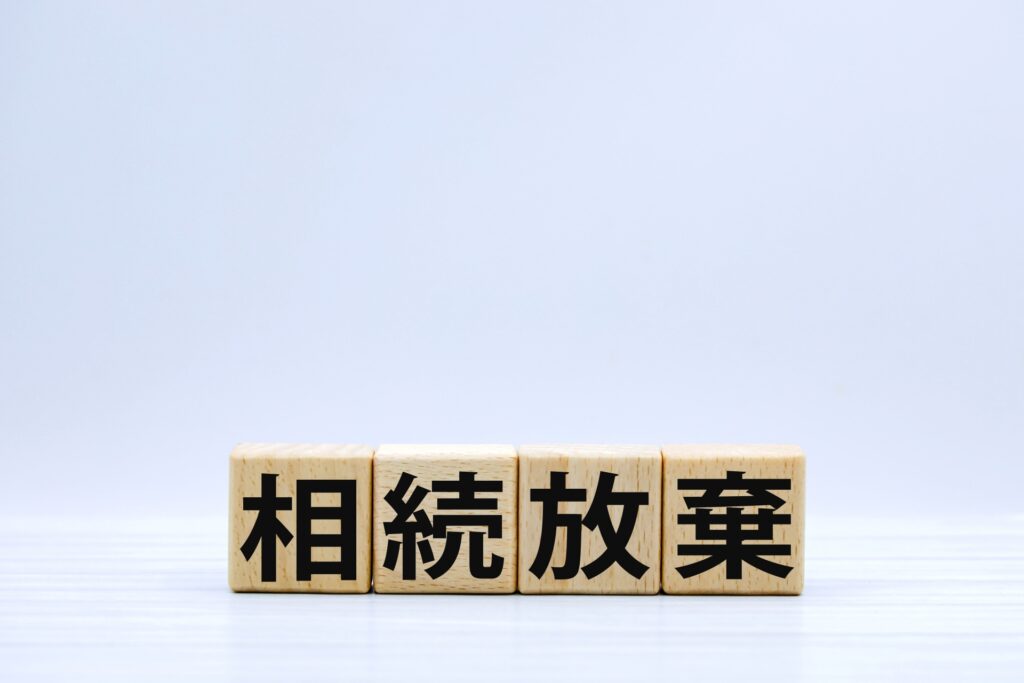
以下のようなケースで相続放棄が行われ、認められることがあります。
最も一般的な相続放棄の理由は、被相続人に借金や負債が多く、財産を相続すると負担が大きくなるケースです。相続放棄を行うことで、借金や負債を一切引き継がずに済みます。たとえば、親が事業の失敗で多額の借金を抱えて亡くなった場合、子供がその負債を相続しないために相続放棄を選択することができます。
被相続人が持つ財産よりも負債の額が多い場合も、相続放棄が行われます。たとえば、被相続人が自宅や土地を所有しているものの、同時に多額の借金を抱えており、相続しても負債の方が大きい場合、相続人は放棄を選ぶことがあります。
被相続人が遺言書を残し、特定の相続人にすべての財産を譲る旨が書かれている場合、他の相続人がその意向に従い相続放棄を行うことがあります。これにより、遺言書通りに相続を行い、相続人間の争いを避けることができます。
遠い親族や面識のない親族が亡くなり、相続人として指名された場合でも、相続放棄を行うことがあります。たとえば、疎遠になっていた叔父や叔母が亡くなった場合、その相続人となる可能性がありますが、財産や負債の状況が分からない場合、相続放棄を選択することが多いです。

以下の場合、相続放棄が無効とされる可能性があります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に手続きを行わないと、無効となります。この期限を過ぎると、相続放棄が認められず、財産や負債を引き継ぐことになります。
相続財産を一部でも使用したり、処分したりした場合は、相続を承認したと見なされ、相続放棄ができなくなります。たとえば、被相続人の預貯金を使ったり、不動産を売却した場合は、相続放棄はできなくなります。
相続放棄が認められた後に、相続財産を受け取る行動を行った場合、相続放棄の効力が失われることがあります。たとえば、相続放棄を行ったにもかかわらず、他の相続人とともに相続財産を分けたり処分した場合、相続放棄が無効となることがあります。

相続放棄を行うためには、家庭裁判所での手続きが必要です。以下のステップで進めます。
相続放棄を希望する場合は、相続開始を知った日から3か月以内に、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出します。
申立てには、以下の書類が必要です。
家庭裁判所は、相続放棄申述書を受理した後、相続放棄の内容について審査を行います。場合によっては、相続人に対して確認のための面談や電話連絡が行われることもあります。
家庭裁判所が相続放棄を認めると、その内容が正式に認定され、相続人は相続放棄が成立します。
相続放棄は、被相続人の財産や負債を引き継がずに済む重要な選択肢ですが、期限内に手続きを行うことや、財産を処分しないことなど、注意すべきポイントがあります。借金や負債が多い場合や、財産より負債が上回る場合、または特定の相続人にすべてを譲りたい場合などには、相続放棄が有効です。
相続放棄を行う場合は、期限内に正確な手続きを進め、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。
【関連動画】相続手続は専門家に任せるべき?【相続のための弁護士チャンネル】
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有
交通アクセス:
電話受付時間:
平日 9:30~18:00
電話番号:
06-6131-0288
対応エリア:
全国各地
相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。