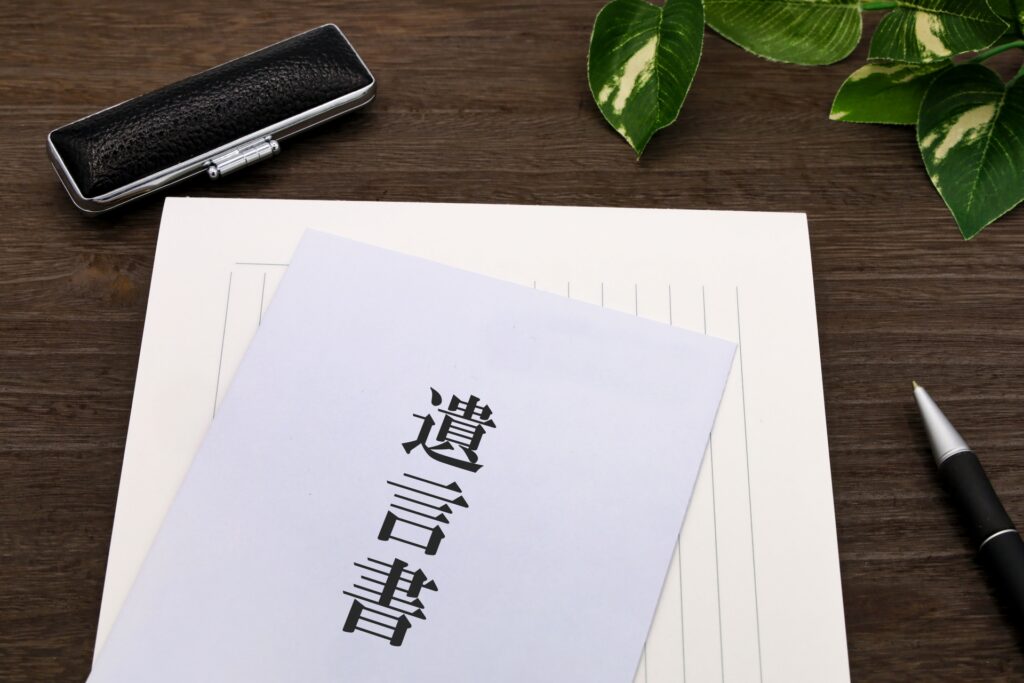親が亡くなった後、感情的なショックと共に、現実的な手続きや相続に関する重要な課題に直面することになります。相続手続きは多くのステップがあり、時間もかかりますが、期限が定められているものも多いため、迅速かつ的確に対応することが求められます。今回は、親が亡くなった後に最初にやるべき5つのことを、相続手続きの全体の流れと共に詳しく解説します。
【関連動画】相続で揉めないために今できること 【相続のための弁護士チャンネル】
目次
1. 死亡届の提出

親が亡くなった際に最初に行うべき手続きは、死亡届の提出です。これは法律に基づく義務であり、親の死亡が確認された日から7日以内に、市区町村役場に届け出を行う必要があります。死亡届の提出を行うことで、葬儀や火葬などの手続きも進められるようになります。
- 必要書類:死亡届と医師が発行する死亡診断書。この2つの書類は通常セットで医療機関から受け取ります。死亡届は遺族が署名し、医師の証明が入った死亡診断書と一緒に役場へ提出します。
- 提出先:死亡届は、死亡地、または亡くなった方の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。この手続きが完了すると、火葬許可証が発行され、葬儀が執り行えるようになります。
死亡届の提出は、親族にとって初めて直面する法的な手続きです。遅延がないように迅速に対応しましょう。
2. 遺言書の確認

次に行うべき重要な手続きは、遺言書の確認です。遺言書の有無は、相続手続きの流れに大きな影響を与えるため、必ず確認しましょう。
- 遺言書の確認方法:自宅内の金庫や書類保管場所、銀行の貸金庫、信託会社などを探します。2020年から導入された「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に保管している可能性もありますので、法務局に問い合わせて確認することも重要です。
- 遺言書が見つかった場合:遺言書があった場合、特に自筆証書遺言や封印されている遺言書は、勝手に開封せずに家庭裁判所に持参して検認手続きを行わなければなりません。検認は、遺言書の有効性やその内容を確定するための手続きであり、全相続人が確認できる場を設けることが目的です。公正証書遺言の場合は、検認は不要です。
- 遺言書がない場合:遺言書がない場合は、法定相続に基づき、相続人全員で財産を分割することになります。この場合、相続人の確定が必要です。
遺言書の存在が相続の方向性を大きく左右するため、慎重かつ確実に確認を行いましょう。
3. 相続人の調査と確定
遺言書があればそれに基づいた相続が進みますが、遺言書がない場合、法律に基づく法定相続人の確定が必要です。相続人を正確に把握しておくことは、手続き全体をスムーズに進めるために非常に重要です。
- 法定相続人の範囲:法定相続人は、まずは亡くなった親の配偶者が含まれ、次に子供が優先されます。子供がいない場合、直系尊属(両親など)や兄弟姉妹が相続人となります。
- 戸籍謄本の取得:被相続人(亡くなった親)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があります。これにより、法定相続人を正確に確定し、相続手続きを進めることができます。また、子供がいない場合や離婚、再婚があった場合など、複雑な家族構成がある場合も確認が必要です。
- 相続人の調査の重要性:相続手続きでは、相続人全員の同意が求められる場面が多く、全員がそろわないと進められないことが多いため、最初に相続人を確定することが非常に重要です。また、相続人が未成年である場合や、行方不明の相続人がいる場合、代理人を立てるなどの手続きを検討する必要があります。
【関連動画】親が亡くなった後、最初にやるべき5つのこと【相続のための弁護士チャンネル】
4. 財産と負債の調査
次に進めるべきは、財産と負債の調査です。相続する財産が何か、どれだけあるのか、また負債がどれくらい存在するのかを把握し、正確にリストアップすることが大切です。
- 財産の種類:相続対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株式、生命保険、有価証券などがあります。一方で、ローンや借金、税金の滞納など、マイナスの財産である負債についても同様に確認する必要があります。
- 調査方法:財産については、不動産登記簿謄本、預金通帳や証券会社の口座明細、保険証券などから確認します。負債については、ローン明細や借入契約書、クレジットカードの明細などを確認します。
- 銀行や金融機関への通知:親が利用していた銀行や金融機関にも死亡の事実を伝え、預貯金口座を凍結する必要があります。銀行口座の凍結後は、相続手続きが完了するまで現金の引き出しができなくなるため、葬儀費用などの支出に備えておくことが大切です。
財産と負債を正確に調査し、相続する資産の全体像を把握することで、後の相続放棄や限定承認の判断がしやすくなります。
5. 相続放棄や限定承認の検討
財産の全容が把握できたら、相続をどうするかを決定することになります。親の財産が多額の借金や負債を含んでいる場合、相続をそのまま受けると借金を背負うリスクがあります。このような場合、相続放棄や限定承認という手続きを検討します。
- 相続放棄:相続放棄をすることで、親の財産(プラスの財産とマイナスの財産両方)をすべて放棄します。家庭裁判所に申述を行い、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この手続きを行うことで、相続人としての立場が失われ、借金を引き継がずに済みます。
- 限定承認:限定承認は、親の財産の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。つまり、親の財産がプラスの場合はそれを相続し、マイナスの財産(借金)はそれ以上負担しないという制度です。この手続きを行うには、相続人全員の同意が必要であり、こちらも家庭裁判所での手続きが必要です。限定承認は、財産の全容が不明な場合や、負債が財産と同程度であると見込まれる場合に検討されるべき手段です。
【関連動画】相続放棄と限定承認の違いを解説【相続のための弁護士チャンネル】
6. 相続や手続きに関するご相談はこちらまで
相続手続きには期限があるものが多く、遅れると権利が失われたり、不利な立場に立たされる可能性があります。複雑な相続手続きを円滑に進めるためには、弁護士や税理士、不動産鑑定士などの専門家に早めに相談することが重要です。
弁護士法人ニューステージ
事務所所在地:
〒530-0026 大阪府大阪市北区神山町1番7号 アーバネックス神山町ビル4階
※近くにコインパーキング多数有
交通アクセス:
- 大阪市営地下鉄堺筋線「扇町駅」(2-A番出口)徒歩5分
- JR環状線「天満駅」徒歩6分
- 大阪市営地下鉄谷町線「中崎町駅」(1番出口)徒歩10分
- 泉の広場(M10階段右上がる)徒歩6分
電話受付時間:
平日 9:30~18:00
電話番号:
06-6131-0288
対応エリア:
全国各地
相続に関する不明点や不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。